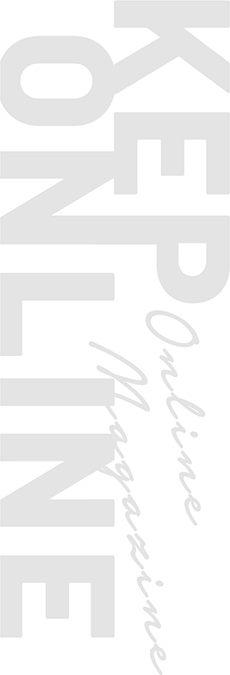

2025/10/22
インタビュー
英国オックスフォード大学の数多いカレッジ合唱団のなかで、マートン・カレッジ合唱団は比較的歴史が新しく、2008年10月に設立された混声合唱団だ。12月の初来日を前に、音楽監督のベンジャミン・ニコラス氏にお話をうかがった。
オックスフォードやケンブリッジの大学の合唱団といえば、男声のみの合唱のイメージが強いが、その伝統も変化してきていると、ニコラス氏は話す。
「たしかに伝統的に大学や大聖堂の男声のみの聖歌隊が有名ですが、今ではオール男声のグループは本当に少なく、ケンブリッジのキングス・カレッジとウェストミンスター寺院の聖歌隊ぐらいで、あとはどこも女性歌手も加わるようになりました。マートン・カレッジには混声合唱団とは別に、少女聖歌隊もあります。伝統はつねに更新されているのです」
マートン・カレッジといえば、天皇陛下が皇太子時代に学ばれた学寮としても知られている。昨年、天皇皇后陛下が英国をご訪問された折にはマートン・カレッジを再訪し、チャペルでオルガンの演奏をお聴きになった。そのときに演奏したのがニコラス氏だ。

「マートン・カレッジのチャペルは、オックスフォードでも有数の美しい建物であり、まちがいなくもっとも音響の良いチャペルです。それは合唱団の響きにさらに輝きを与えてくれる最高の場なのです」
その響きの良さから、タリス・スコラーズらプロのアンサンブルが録音や公演で使っていたが、それならばカレッジに常設の合唱団を創設しようということになったのだという。
合唱団の構成と普段の活動についてうかがった。

「合唱団は30人の学部生、大学院生から構成されています。男女比はほぼ半々で、ソプラノは女声、アルトは女声とカウンターテナーが両方います。学期中は毎週3回の夕方の礼拝(イーブンソング)と、2週間に一回の日曜日のミサで歌います。そして、大学の休暇中には、今回のように演奏旅行を行ったり、レコーディングしたり、礼拝以外の活動も行います。いろいろな専攻の学生たちから成っていて、音楽専攻もいますし、法学、物理学や化学、建築、言語学など多岐にわたっています。全員が声楽の個人レッスンを受け、響きの豊かな声で歌うことを学びます。卒業後は、音楽家になる人もいれば、一般企業に就職する人もいて、さまざまです」
合唱団の響きの特徴については、「チャペルの響きにある程度規定されるわけですが、ふだんチャペルで歌う際にはヴィブラートの多すぎないクリアな音が求められるので、ピュアかつ明瞭で、響きの豊かなサウンドだと言えるでしょう」と語る。
「また合唱団の大きな特色はレパートリーの広さです。礼拝で歌うバードやビクトリアなどのルネサンス時代の音楽から、ハウエルズやパリー、ジョン・ラターやG.ジャクソンら現代の作曲家のものまで、幅広いスタイルの曲をカバーしています」
ニコラス氏自身もノリッジ大聖堂の聖歌隊出身で、オックスフォードでオルガン・スカラーとして学んでおり、とりわけ英国の合唱音楽には造詣が深い。
日本でのプログラムはクリスマス・シーズンを念頭に置いたもの。前半にバード、トムキンス、ビクトリア、バッハなどの宗教曲、そして後半には英国で愛唱されているクリスマス・キャロルが並ぶ。しかも、なんと「オー・ホーリー・ナイト」や「きよしこの夜」は、マートン・カレッジとゆかりの深いラターの編曲で歌われる。

「今回は多彩なプログラムを用意しました。それぞれの曲にふさわしい響きでお届けできたらと思います。みなさんにとって初めての曲もあるでしょうし、耳馴染みの曲もあると思いますが、それがコンサートの醍醐味ではないでしょうか」
最後に、ツアーへの抱負を語っていただいた。
「大学の合唱団では新年度にメンバーが3分の1入れ替わるので、新しい団員を迎えてそこから12月に向けていかに準備できるかが鍵となるでしょう。合唱団にとっても私にとっても日本で演奏するのは初めてです。学生たちには滞在中にぜひ日本の文化全般について――食文化はもちろんですが、風習、生活様式、建築なども含め――多くのことを吸収してもらいたいと思っています。きっとこのツアーを通して大きく成長してくれるでしょう。日本各地のすばらしいホールで演奏できることを心から楽しみにしています」
(後藤 菜穂子)

オックスフォード
マートン・カレッジ合唱団
~オックスフォードのクリスマス~
■出演
オックスフォード マートン・カレッジ合唱団
■指揮
ベンジャミン・ニコラス
■ナビゲーター
三代澤康司
■ゲスト
関西学院グリークラブ
|日時|2025/12/10(水) 15:00
|会場|東大阪市文化創造館 Dream House 大ホール
▶▶公演詳細